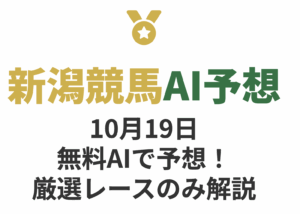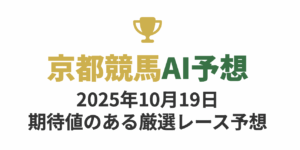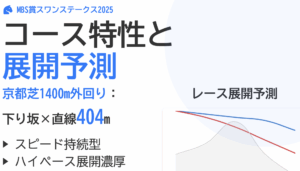三冠の最終決戦・菊花賞(芝3000m)は、クラシック最後の栄冠をかけた長距離戦です。
しかし、過去10年のデータを振り返ると、1番人気馬が必ずしも信頼できるとは限りません。
実際、この10年で1番人気が勝ったのはわずか3回。
残る7回は人気を裏切る結果に終わっており、4回は馬券圏外に沈んでいます。
一方で、5番人気前後の伏兵が何度も馬券に絡んでおり、 「実力通りに決まらないレース」という傾向も明確です。
距離3000mという舞台、展開の読み、仕上がりのタイミング。
これらの条件が少しでも噛み合わないと、どれだけ能力があっても勝ち切れない。
それが、菊花賞の本質と言えるでしょう。
今年もまた、一頭の“主役候補”が注目を集めています。
神戸新聞杯を驚異的な末脚で制したエリキング。
ルメール騎乗のエネルジコ、友道厩舎のショウヘイなどと並んで人気の中心となりそうですが、 本当にこの馬は「信頼に足る1番人気」なのか。
過去の1番人気敗退馬の共通点を検証しながら、 今年のエリキングに潜むリスクを探っていきます。
過去の「1番人気敗退馬」に共通する5つの危険なサイン
サイン1:距離適性という“3000メートルの壁”
最も多く見られるのが、距離適性の問題です。
菊花賞の3000メートルは、ダービーの2400メートルとも、 有馬記念の2500メートルとも違う独特のタフさがあります。
2019年のヴェロックス(川田騎手)は、 皐月賞2着・ダービー3着という安定感で1番人気に推されましたが、 直線では脚色が鈍り3着止まり。
レース後、川田騎手は「最後は距離が長かった」と述べています。
また、2023年のソールオリエンスも皐月賞馬として期待されながら、 終始後方からの競馬で3着に敗れました。
横山武史騎手も「距離が少し長かったかもしれない」とコメントしており、 長距離適性の壁に苦しんだ代表例です。
スタミナだけではなく、折り合いと精神的な持続力が問われるのが菊花賞。
ペースが落ち着く中盤で気負ったり、コーナーでリズムを崩したりすると、 最後の直線で力を発揮できません。
どんな名馬でも、初めての3000メートルでは“未知の壁”と向き合う必要があります。
そしてその壁こそが、人気馬を飲み込んできたのです。
サイン2:展開とペースの罠、マークされる人気馬の宿命
もう一つの敗因が、展開の読み違いです。
菊花賞は年によってペースが大きく変わり、 上がり勝負になる年もあれば、スタミナを問う持久戦になる年もあります。
2023年のドゥレッツァ(ルメール騎手)は、 スローペースを読んで早めに動き、4番人気ながら見事な押し切り勝ち。
一方で、1番人気のソールオリエンスは後方で脚をためす競馬を選び、 直線で届かず3着。
展開の読みが勝敗を分けた典型例です。
また、2024年のダノンデサイルも1番人気に推されながら、 スローペースの外々を回る形になり6着。
横山典弘騎手は「流れが悪すぎた。可哀想だった」とコメントしており、 位置取りとペース配分のズレが大きく響いたことが分かります。
人気馬は他陣営からマークされやすく、自分のリズムで運びにくい。
これも、1番人気が取りこぼす大きな要因の一つです。
サイン3:ローテーションと仕上がりの落とし穴
菊花賞のローテーションは非常に重要です。
過去10年を見ても、「前走・神戸新聞杯」「前走・セントライト記念」など、 前哨戦を一度叩いてきた馬の好走が目立ちます。
一方で、日本ダービー以来の直行組は苦戦傾向。
レース間隔が空くことで、実戦勘やスタミナの持続が狂うケースが多いからです。
例えば2024年のダノンデサイルはダービー以来5か月ぶりの実戦で菊花賞に臨みましたが、 直線で反応が鈍く6着。
「実力上位でも仕上がりひとつで敗れる」ことを示した一戦でした。
エリキングは神戸新聞杯を快勝して本番に臨む王道ローテーションですが、 春の皐月賞では11着、日本ダービーは5着と苦戦が続きました。
春から夏を経て状態がどこまで上向いているかが、 信頼度を左右する鍵になるでしょう。
サイン4:夏を越えた“世代勢力の変化”と新興勢力の台頭
春のクラシックで活躍した馬が、秋になって別の馬に抜かれる。
この「勢力図の変化」も菊花賞では頻発します。
2018年の例が象徴的です。
皐月賞馬エポカドーロは3番人気に推されましたが、 7番人気フィーエルマンが一気に頭角を現し優勝。
ブラストワンピースが1番人気で敗れた背景にも、 「夏に急成長した馬の台頭」がありました。
菊花賞は、春の実績だけでは測れないレース。
秋になって馬体が締まり、精神的にも成熟してきたタイプが台頭する舞台です。
つまり、春の序列がそのまま秋に通用しない。
今年のエリキングも、他の馬の「成長分」を過小評価すると痛い目を見る可能性があります。
サイン5:騎手のプレッシャーとレース相性という“人の壁”
最後に見逃せないのが、騎手とレースの相性です。
川田将雅騎手は日本を代表する名手でありながら、 菊花賞では2010年のビッグウィーク以来勝利がありません。
2019年のヴェロックス(1番人気3着)以来、惜敗が続いており、 「どうしても勝ち切れない」舞台の一つと言えるでしょう。
また、1番人気の馬は常に他陣営からマークされ、ペースを握られやすい。
「勝たなければならない」という立場の重圧もあり、 少しの判断ミスが命取りになります。
エリキング陣営にとっても、この“人気馬の宿命”をどう乗り越えるかがテーマになります。
今年の主役・エリキングの評価:血統と脚質に潜むリスク
エリキングは、神戸新聞杯を驚異の上がり32.3秒で制し、 現時点で世代トップ級の力を示しました。
父キズナ、母父High Chaparralという血統もスピードと瞬発力に優れ、 3000mでも期待できる素材です。
ただし、キズナ産駒は長距離GⅠの勝利例が少なく、 持続力勝負になると不安を残す点もあります。
また、春は皐月賞11着、ダービー5着と“勝ち切れない”レースが続いています。
気性面の難しさや、展開に左右されやすい脚質もあり、 「能力は高いが条件次第で崩れる」タイプであることは否めません。
神戸新聞杯での圧勝が本物であれば、その勢いのまま戴冠も可能。
しかし、過去の1番人気敗退馬たちも同じように“前哨戦の勝ち方”で高く評価されながら、 本番で崩れてきたという歴史があります。
3000mという舞台で、再びそのジンクスが顔を出す可能性は十分にあります。
結論:エリキングは信頼度が高いが「絶対視」は禁物な理由
エリキングは実力・完成度ともに今年の主役候補であることは間違いありません。
神戸新聞杯を制した勢い、川田騎手とのコンビ、調教内容などを総合すれば、 勝ち負けの中心になるのは確実でしょう。
しかし、過去の1番人気馬が敗れてきたパターンと照らすと、 彼にもいくつかの「危険な共通点」が見えてきます。
3000mという未知の距離への不安。
展開に左右されやすい脚質。
春の敗戦歴とメンタル面のムラ。
他馬の成長による勢力変化。
1番人気ゆえのマークと重圧。
これらを踏まえると、エリキングは“信頼できる軸”ではあるが、 “絶対的な本命”とは言い切れません。
むしろ、2〜3番人気の実力馬や、 夏を越えて急成長した伏兵にも十分にチャンスがある構図です。
菊花賞は、実力だけで勝てるレースではありません。
距離、展開、成長度、仕上がり、そして運。
さまざまな要素が絡み合い、人気馬の牙城を崩してきた歴史があります。
今年のエリキングは、間違いなくその中心にいる存在ですが、 同時に「最も崩れやすい立場」でもあります。
本当に信頼できる主役かどうか。
その答えは、京都の直線で明らかになるでしょう。