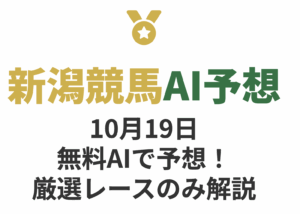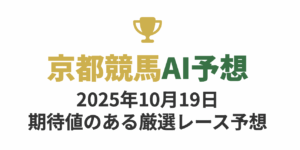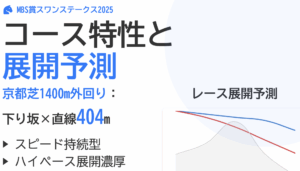菊花賞(GⅠ・芝3000m)はクラシック三冠の最終戦であり、伝統的に「最も強い馬が勝つ」と語られてきました。
ただし正確に言えば、日本の平地GⅠで最長距離なのは天皇賞(春・3200m)。
菊花賞は3歳クラシック三冠の中で最長距離に位置づけられ、 若駒にとっては「スタミナと精神力を問われる最初の長距離決戦」です。
この舞台では、スピードや瞬発力だけでなく、折り合い・持続力・展開適性といった総合力が試されます。
そのため“本当に強い馬が勝つ”という定説が語られる一方で、 展開次第で“格下の馬が格上を逆転する”現象も頻発するのが菊花賞の面白さです。
菊花賞は「最も強い馬が勝つ」舞台という定説を疑う
3歳馬をふるいにかける3000mという距離の過酷さ
菊花賞が「最も強い馬が勝つ」とされる最大の理由は、 3000mという距離そのものにあります。
皐月賞(2000m)のスピード、日本ダービー(2400m)の総合力と運が試された後、 最後に待ち受けるのがこの長距離戦です。
3歳春の時点では、多くの馬が本質的にマイラーや中距離馬としての適性しか見せていません。
その馬たちが、秋になり成長したとはいえ、いきなり3000mという未知の距離に挑むのです。
ここでは純粋なスピードだけでは通用せず、レース中盤でいかにスタミナを温存できるか(折り合い)、 そして最後の長い直線と急坂(阪神開催時)や、京都の平坦な直線を走り切る底力が問われます。
この過酷な条件をクリアできるのは、心身ともにタフで、 世代トップクラスのスタミナを持つ馬に限られるため、「強い馬が勝つ」と言われるのです。
過去10年の傾向分析「勝ち馬は堅実、馬券は波乱含み」
では、オッズ通りに決まるのでしょうか。 過去10年(2014〜2023)の結果を見ると、興味深い傾向が浮かび上がります。
まず、勝ち馬の多くは上位人気です。 1〜3番人気馬が勝ったのは10年中7回と、信頼度は比較的高めです。
しかし、馬券的には決して平穏ではありません。
2017年は1番人気キセキが勝ちましたが、10番人気・13番人気が2・3着に入り、3連単559,700円の大波乱。 2018年は7番人気フィエールマンが勝利し、3連単104,890円となりました。
2015年のキタサンブラック(3番人気勝利)の年も、1番人気が着外に敗れています。
つまり、勝ち馬は能力通り上位人気に偏るが、2・3着には伏兵が入りやすい、 これが菊花賞の近年の特徴です。 特に「展開が極端に偏った年」は配当が跳ね上がります。
逆に、標準的なペースで直線勝負になった年は、 人気上位馬が順当に上位を独占しており、“波乱か堅実か”を分けるのは展開そのものなのです。
展開の分岐点「京都3000m」コース特性とペースの関係
なぜスローペースからのロングスパート戦になりやすいのか
菊花賞の展開を左右するのが、京都競馬場・芝3000m(外回り)という特殊なコース形態です。
スタート地点は向こう正面の真ん中やや右。 そこから最初の3コーナーまでの距離が長いため、 序盤で無理なポジション争いが起きにくく、ペースが落ち着きやすいのが最大の特徴です。
中盤まではゆったりとした流れ(スローペース)になりがちで、各馬はスタミナを温存します。
そして勝負所は、2周目の3コーナー手前にある「下り坂」です。
この下りを利用して各馬が一斉にペースアップを始めるため、 最後の直線入り口を迎えるずっと手前から、非常に長い持続力勝負(ロングスパート戦)が繰り広げられます。
この“下りを利用した長い脚の使い合い”こそが、 展開利とスタミナの交錯点となるのです。
馬場状態で一変する「スタミナ勝負」と「瞬発力勝負」
同じ3000mでも、レースの質はペースと馬場状態で180度変わります。
まず、良馬場で時計が出やすい「高速馬場」の場合。 序盤がスローペースになればなるほど、各馬はスタミナを温存できます。 勝負は最後のロングスパート、あるいは直線だけの瞬発力勝負になりがちです。 この場合、「切れる末脚」を持つ馬、つまり中距離路線で実績のあるスピードタイプが台頭しやすくなります。
逆に、雨で時計がかかる「タフな馬場(重馬場・不良馬場)」の場合。 3000mを走るだけでスタミナが削られる消耗戦となります。 こうなると瞬発力は意味をなさず、バテずに最後まで走り切れる「底力と持続力」がモノを言います。
つまり、同じ3000mでも、 「速い流れ(またはタフな馬場)」か「緩い流れ(または高速馬場)」かで、 求められる資質が「スタミナ」と「瞬発力」にまったく異なるのです。
過去の菊花賞に見る「展開利」が起こした逆転劇の実例
2018年フィエールマン:超スローが呼んだ「瞬発力」の逆転
「展開利」がスタミナの序列を覆した典型例が、2018年のフィエールマン(7番人気)です。
この年は1000m通過が62.7秒という、長距離戦ではあり得ないほどの超スローペースで流れました。
全馬がスタミナを全く消耗しないまま、まるで「ヨーイドン」の競馬となり、 勝負は最後の直線での瞬発力比べに。
キャリアわずか3戦、長距離未経験でスタミナが未知数だったフィエールマンですが、 上がり3ハロン(最後の600m)で最速の33.9秒という驚異的な末脚を繰り出し、差し切り勝ちを収めました。
これは3000mのスタミナ勝負ではなく、実質的には中距離の瞬発力勝負となったためであり、 距離不安を展開利で完全に打ち消した、まさに“逆転の瞬発力”でした。
2017年キセキ:不良馬場が証明した「持久力」の価値
2018年とは対照的なのが、前年の2017年、キセキ(1番人気)が勝利したレースです。
この年は台風の影響で、稀に見る「不良馬場」での開催となりました。
重い馬場に脚を取られ、全馬がスタミナを消耗するタフな持久戦。 瞬発力やスピードは一切通用しません。
キセキは中団から早めに動き、他馬がバテていく中でただ一頭、 力強いロングスパートを持続させて圧勝しました。
このレースは、展開(馬場)が「純粋なスタミナと底力」を要求した結果であり、 2着・3着には人気薄(10番・13番人気)のスタミナ自慢が食い込みました。
キセキの地力の高さはもちろんですが、展開が持久力勝負に振り切れたことが、 その強さを最大限に引き出したと言えます。
2010年・2023年:展開を味方にした「先行力」の勝利
スローペースの恩恵を受けるのは、差し馬だけではありません。 前に行く馬にとっても、展開利は大きな武器となります。
2010年のビッグウィーク(7番人気)は、道中がスローペースになったことで、 逃げ馬が淡々と楽なペースで主導権を握る展開となりました。
ビッグウィークは先行策から、直線でそのまま後続を振り切って押し切り勝ち。 末脚勝負では分が悪かったものの、展開利を最大限に活かし、 上位人気と目されたローズキングダム(2番人気)らの追撃を封じ込めました。
2023年のドゥレッツァ(4番人気)も同様のパターンです。 平均ペースから自ら動いて主導権を握ると、 上がり最速タイの脚を使って後続を完封しました。
皐月賞馬やダービー馬といった強力なライバルたちを抑え、 逃げ・先行の立ち回り+持続力を兼ね備えた「展開対応型」が完勝した好例です。
菊花賞で勝つための重要なファクター
「上がり最速馬」は信頼できるか?京都3Bの仕掛け所
京都開催の菊花賞では、上がり最速馬の成績が非常に優秀です。 過去8回のうち7回は、上がり最速をマークした馬が連対(2着以内)しています。
唯一の例外は2016年のディーマジェスティ(上がり最速で4着)でした。 つまり、末脚の鋭さが結果に直結することはほぼ間違いありません。
しかし、なぜ届かないケースがあるのか。 それは、京都外回りコースの仕掛け所に秘密があります。
勝負所の3コーナーから4コーナーは下り坂になっており、ここでペースが上がります。 直線は平坦で約400m。
極端な後方一気の戦法では、 先行勢が下り坂で加速しているため、追いつけないリスクがあります。
いかに速い上がりを使えても、「下り坂で加速できる中団〜前目の位置」にいることが重要であり、 “脚の質”だけでなく、“使うタイミングと位置取り”こそが勝敗を分けるのです。
長距離戦は「人」で買え 菊花賞を制する騎手の技術
3000mという長距離戦では、馬の能力と同じくらい、 騎手の判断力とペース感覚が極めて重要になります。
馬をリラックスさせてスタミナを温存させる「折り合い」。 レース全体の流れを読む「ペース判断」。 そして、勝負所(3コーナーの下り)で仕掛ける「タイミング」。
これら「人間のスタミナ戦」とも言える駆け引きが、着順に直結します。
過去10年を見ると、C.ルメール騎手が3勝(2016年サトノダイヤモンド、2018年フィエールマン、2023年ドゥレッツァ)とトップの成績です。
どの勝利も、馬の能力を信じ、 スローペースでも焦らず脚を溜める冷静な判断が光りました。
そのほか、武豊騎手、川田将雅騎手、横山典弘騎手といった、 馬のリズムを第一に考える“長距離巧者”が好結果を出している点も、 菊花賞が「人馬一体」のレースであることを示しています。
結論:「展開」こそが3歳馬の真の強さを映し出す鏡
菊花賞予想で注目すべきチェックポイント
菊花賞を読み解くためには、単純な能力比較だけでは不十分です。 以下のポイントを総合的にチェックし、展開を予想することが鍵となります。
- ペース想定 逃げ馬不在ならスロー濃厚。瞬発力タイプが浮上します。 逆に逃げ・先行馬が多ければ平均〜ハイペースとなり、スタミナと粘り強さの勝負になります。
- 馬場傾向 良馬場なら“瞬発戦”、雨で時計がかかれば“持久戦”と割り切りましょう。 特に重馬場の年は、前に行く馬が有利になりやすい傾向があります。
- 位置取りと下り坂の使い方 京都の3コーナー(下り坂)でスムーズに加速できる、中団あたりにつけられそうな馬は有利です。 大外を回されると、その分だけスタミナをロスします。
- 折り合い力 3000mは精神面との戦いです。レース前にイレ込んだり、道中で力んだりする(かかる)馬は、 スタミナを無駄遣いし、最後で必ず脚が止まります。
- 血統背景 父や母の父にステイゴールド系やハーツクライ系といったスタミナ型種牡馬を持つ馬は、 消耗戦になっても安定しています。 逆にディープインパクト産駒などの瞬発型は、スローペースで展開利を得たときに逆転する傾向があります。
まとめ:展開を読み切り「真の強さ」を見抜け
菊花賞は一見するとスタミナ勝負に見えますが、 その実態は、レース展開によって“問われる能力”が真逆に変わる、非常に奥深いレースです。
スローペースになれば、瞬発力と位置取りが勝敗を分けます。 消耗戦になれば、スタミナと根性が勝敗を分けます。
そこには、展開利を得た馬が、世代トップクラスと目された格上馬を逆転する余地が常に存在します。
ゆえに、菊花賞における「本当に強い馬」とは、 単にスタミナがある馬ではありません。
どんな展開にも対応できる柔軟性。 どんなペースでも折り合える精神力。 そして、勝負所で自ら流れを支配できる総合力。
それらすべてを兼ね備えた存在こそが、 三冠最終戦・菊花賞で王者となる資格を持つ馬なのです。